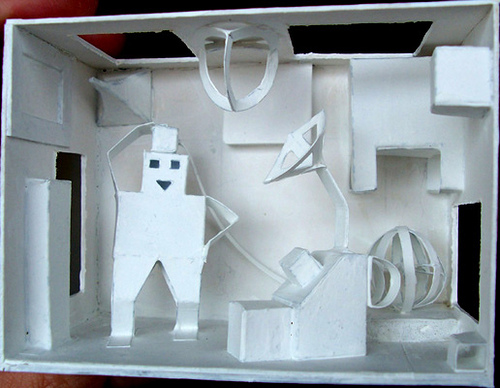もし、文系に「チョコレートを買ってきて」と言えば、「チョコレート」を買ってくるだろうが、理系に同じ事を言ったなら、矢継ぎ早に質問が来るだろう。「原材料は?大きさは?味は?価格帯は?使用用途は?・・」。
「チョコレートとは何か」を理解して、期待された結果を出すために必要な情報を得ようとするからで、それらの情報がなければ「チョコレート」が何かが知識としてはわかっていても、求められたものがわからない「問題」であるから、この問題を解こうとしている。
逆に言えば、文系にとって「チョコレート」は「チョコレート」であって、求められているものかどうかは不問であり、言われるがままに分類や名称がチョコレートと言われるものはすべて正答になる。これを正答とするには、自分自身の判断など曖昧な要素を多分に加える必要がある。
対して理系は、まず、ここで言う「チョコレート」とは何かから始まる。決して「チョコレート」を知らないわけではない。言い方を変えれば、相手の望む結果は何かを理解しようとして、情報を収集し、期待された結果と期待した結果を一致させようとする。
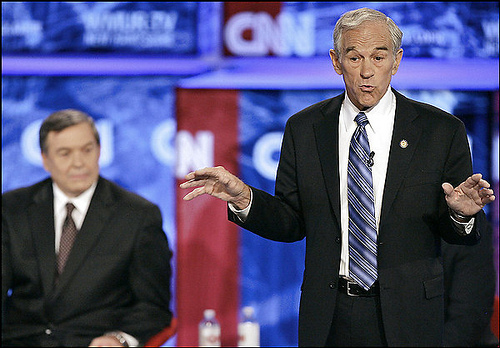
つまり、文系に注文したチョコレートはチョコレートだが、期待したチョコレートでない可能性が高い。一方、理系に注文して適切に質問に回答したチョコレートは、完全にチョコレートである可能性が高い。
言い方を変えれば、文系の結果は流動性があるのに対して、理系の結果は流動性が無いと言える。
たまたま通りかかった所で「チョコレートと言えなくもない」チョコレートを見かけたら、それを購入することで了とするか、それとも、それは正しい結果を得られないとして、「正しい結果を得られるチョコレート」を探しまわるかの違いがある。
氏は、これを極端に表現したものと思われ、流動性の有無を結果の流動性に置き換えているように感じる。
また、同時に「理系は、楽しそうだ」とも言う。